御茶ノ水駅に登場したJR東日本のポスターが「AIっぽい」とSNSで炎上しました。
いや最初から「AI作成」って書いてあるのにバレバレかい!と突っ込みたくなる展開ですよね。
なぜ人々は違和感を抱いたのか?
ポイントは“主役が曖昧な構図”と“日常感のズレ”でした。
ジンギスカンと人物の面積が並列で「どっち見ればいいの?」状態。
さらに両手に箸を持つ二刀流の所作に「そこ!?」と笑いが漏れます。
AIのメリットは安さと速さですが、文化を描くには細部の監修が欠かせません。
つまり炎上の原因はAIそのものではなく、人の目で文脈を調整する工程の不足だったんです。
JR東日本のポスターAI、違和感の核心は?
SNSで出回った画像には「AI作成」との表記が確認されました。
いやいや、最初から正直に書いてあるんかい!と突っ込みたくなりますよね?
それでも「やっぱりAIっぽい」と一目でわかるのはなぜか。
結論はシンプルで、主題と脇役の面積バランス、人物の所作のちぐはぐさ、そして物語性の欠落でした。
料理と人物が同じサイズ感で、何が主役かわからない。
さらに両手に箸を持つ“二刀流”の描写まで登場。
いやそこ!? って感じでしょう。
広告ポスターって、主役をドーンと出すのが鉄則でしょうね。
それがぼやけると「で、何を伝えたいの?」となります。
小物や動作のつながりが欠けると、一瞬で「作り物」っぽさが浮き出てしまうんですよ。
結局このズレが積み重なり、見る人の直感に引っかかったわけです。
舞台に主役がいない芝居みたいな不思議さでしたね。
面積配分と主従、どこがズレ?
あるユーザーは「人とジンギスカンの面積が均等で不自然」と指摘していました。
いやいや、郷土料理を主役にしたいならもっと目立たせなきゃ!でしょう?
人間のイラストレーターなら、巨大なジンギスカンをドーンと描いて、人物は小さめに添える。
なのに並列のままだから「結局どっち見ればいいの?」と迷うんです。
主従関係が見えないと説得力は半減。
全員がセンターに並ぶ学芸会みたいな印象になりますよね。
所作の整合、箸は二刀流なの?
SNSでは「両手に箸はないでしょ」とツッコミが飛んでいました。
タレの位置や生肉の並びもおかしくて、思わず「ちょっと待ってくださいよ(笑)」となる。
食事の流れを想像すると違和感は明らか。
笑顔の表情もシーンと結びつかず、浮いて見えます。
日常の当たり前が守られないと、リアリティは一気に崩れるんですよね。
ここが「AIっぽさ」を嗅ぎ分ける決め手だったのでしょう。
JR東日本のポスターAI、炎上理由の整理
今回の炎上は「表現の質」と「制作手段」が絡み合っています。
でも正直、火をつけたのは“質”の方でしたよね?
箸や視線のズレといった具体的な違和感が先に話題になり、その後に「AI使用だからか」と批判が加速。
つまり「AIだから炎上した」というより、「雑に見えたからAIと紐づけられた」という流れです。
もちろん、AIのメリットもあります。
コストは安く、制作は早く、修正も効く。
いや、それは強いでしょう!
でも、地域文化を扱うなら精度やリスペクトが求められるのも当然ですよね。
要するに、解像度が足りなかったことが炎上の核心でしたね。
コストと速度は利点?
広告実務者からは「安い」「早い」「すぐ直せる」という声が上がりました。
確かにその通りで、短納期では便利でしょう!
ただし、それで全てが解決するわけじゃない。
要件定義や監修が弱ければ違和感は量産されてしまいます。
AIは便利だけど、ちゃんと監督する人間がいなきゃダメなんですよね?
ここが欠けると、利点が一瞬でリスクに変わるでしょうね。
地域リスペクトは不足?
「地元の文化を描くのにAIってどうなの?」という感情的な反発も出ました。
地元にクリエイターがいるのにAI生成とは…ちょっと冷たく映りますよね。
文化を描くときは、単なる絵以上に生活感や作法が大事です。
それが再現されないと「文化を掬ってない」と見られやすい。
地域を題材にした表現こそ、細部の解像度が命。
そこが抜けたことで火種が広がったんでしょうね。
JR東日本のポスターAI、議論が示した答え
議論から見えてきたのは三つ。
構図の主役設定、所作の整合性、物語の繋がり。
結論は「AIが悪い」ではなく「設計不足が悪い」でした。
いや、AIはただの道具ですからね。
面積や所作の矛盾は一貫して指摘され、笑顔の不一致も違和感を強めました。
ここを監修で潰せば炎上は避けられたでしょう。
AIは試作や修正で強みを発揮します。
ただ広告の説得力は、主役の明確化、生活知の監修、画面設計の優先度で決まるんです。
最後にポイントを整理しましょう。
- 主題の面積配分を明確にする
- 所作や器具の整合を守る
- 視線と表情で物語を繋ぐ
- AI使用範囲と検品をはっきり示す
- 地域文化の文脈を尊重する
つまり炎上の理由は「AIのせい」ではなく「監修不足」でした。
広告の説得力は文脈とリアリティの積み重ねで決まるんですよね?


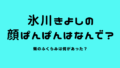
コメント