2025年6月30日放送の『しゃべくり007』で、パンサー尾形さんがビンタを受ける場面が登場。
番組としては“お決まりの笑いの流れ”だったものの、SNS上では「やりすぎ」「時代錯誤」といった声が相次ぎました。
一方で「昔からある演出でしょ?」「何が問題なの?」と擁護する声もあり、意見は真っ二つに。
なぜ、たった数秒の“お笑い演出”がここまで賛否を呼んだのか?
その背景には、視聴者側の“ある心理変化”が見え隠れしています。
今回はこのビンタ演出をきっかけに、バラエティ番組に対する視聴者の意識変化について深掘りしていきます。
SNSで賛否が分かれた理由とは?
まず、SNS上ではどんな意見が飛び交っていたのでしょうか?
SNSコメントから見る“笑えなかった派”の声
番組放送直後から、X(旧Twitter)では否定的な反応が目立ちました。
「笑えない……普通にいじめっぽく見える」
「痛そうだし、なんか可哀想になってしまった」
「令和のバラエティでこれはアウトじゃない?」
など、“やりすぎ感”を指摘する声が一定数見られました。
特に、「今はもう時代が違う」「テレビ側の感覚がズレてる」というトーンが強く、
“バラエティ=安心して笑える場所”であってほしい、という期待の裏返しとも受け取れます。
一方で「昔からある演出」「気にしすぎ」の声も
もちろん、すべてが批判的だったわけではありません。
「むしろ体張ってて面白かった」
「これがダメって、バラエティ作れなくなるよ」
「気にしすぎでは?」
という、“過剰反応を懸念する声”も根強くありました。
つまり、視聴者側の**「笑いの受け取り方の多様化」**が顕著に表れたワンシーンだったのです。
なぜ“お笑い演出”が炎上するのか?
一見「よくあるバラエティの流れ」が、なぜここまで問題視されたのでしょうか?
そこには、近年の視聴者心理の変化が影響しています。
「笑っていいのか分からない」という“視聴者の自問”
今の視聴者は、テレビでの演出を単純に受け止めず、
「これって本当に笑っていいの?」という“自問”を挟む傾向があります。
これはSNS時代ならではの現象で、投稿が炎上する・誰かを傷つけるといった
“二次的なリスク”を常に想定してしまうからです。
つまり、
- 見ている最中にブレーキがかかる
- 純粋に楽しめない
という視聴体験が増えているのです。
その結果、「自分は笑えなかった」という感想が、SNS上で可視化されやすくなります。
バラエティにも“コンプラ感覚”が求められる時代に
加えて、バラエティ番組ですら「コンプライアンス視点」が重視されるようになっています。
芸人や演者がどれだけ“お約束”の演技をしていても、
視聴者が「本気っぽく見えた」「不快だった」と感じれば、それが“事実”として受け止められてしまう。
いまや“演出だからOK”とはならない時代なのです。
「家庭で子どもに見せたくない」という価値観
実は今回の件、子育て層の反応にも注目すべき点がありました。
「子どもが真似したら困る」
「こういうの見せたくないな」
という、家庭内での教育的な視点からのコメントも多く見られたのです。
視聴者が「番組の教育的影響」を気にするようになった?
かつては“テレビ=娯楽”と割り切られていたものの、
今は家庭の中で「どう子どもに影響するか?」という観点で番組を見る親が増えています。
とくに、“暴力表現”や“いじめに見える演出”は、そのまま家庭の教育方針と対立することもあります。
つまり、演出の是非だけでなく、“見せるに値するかどうか”まで評価対象になっているのです。
まとめ|視聴者の“真剣さ”は価値観の多様化の証だった
ここまで見てきたように、
バラエティ番組に対して“真剣に”反応する人たちは、決して間違っているわけではありません。
むしろその感覚こそが、今の時代の変化を象徴しているのかもしれません。
この記事の要点を、あらためて整理しましょう。
- SNS上では、笑いよりも“倫理性”が優先される場面が増えている
- 視聴者の中で「これは笑っていいのか?」という自問が炎上につながっている
- バラエティであっても“コンプラ視点”が求められる時代になった
- 演者のふるまいが“家庭教育”の写し鏡として評価されてしまう風潮がある
- 視聴者の“真剣さ”自体が、多様化した価値観の表れといえる
時代が変われば、笑いの受け取り方も変わる。
かつての“お決まりの演出”が、今は波紋を呼ぶこともある。
けれどそれは、視聴者が“悪くなった”のではなく、
ただそれぞれの視点が、より細やかになっただけなのかもしれません。
誰かにとっては大爆笑、誰かにとっては不快──
そんな「感情の多様化」が、いまのテレビと社会の距離感を物語っているのだと思います。

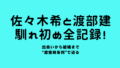
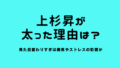
コメント